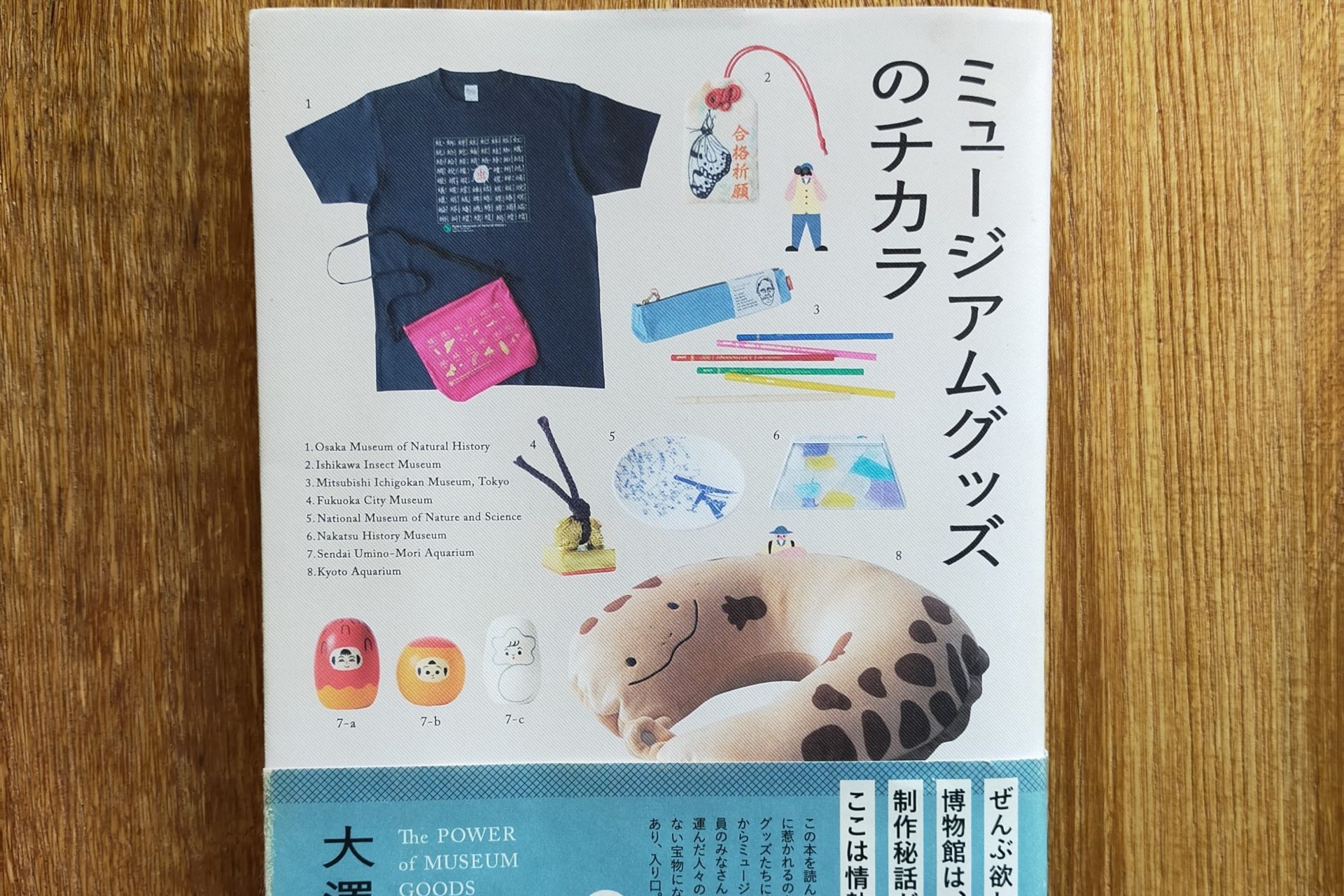- text and edit by
- ウェブ版「カルチベイト」チーム
乃村工藝社グループでは、『Cultivate(カルチベイト)』というオウンドメディアを発行し、社会に対し提言してきました。わたしたちをとりまく「文化環境」のエレメントとしての、「知」や「情報」、「創造性」「コミュニケーション」といったテーマを多面的に考察し、新たな文化の地平を切り開くことをコンセプトに、さまざまな有識者へのインタビューや対談を通じて、これからの「文化環境」のあり方へのアプローチを行ってきました。
その『Cultivate(カルチベイト)』が10年ぶりに、Web版として「ノムログ」で再始動します。地域文化のハブとしての機能を求められているミュージアム。最初のテーマは、その核とも呼ぶべき収蔵庫です。コレクション、そしてそれを展(ひら)いて示すことから始まったミュージアムの、これからのあり方を考えます。
今、収蔵庫は、非常に大きな危機に直面している
「収蔵庫」とは、全国各地にある博物館や美術館、歴史資料館などのミュージアムに備わる機能の一つで、ミュージアムが収蔵するコレクションや資料などを保存するための重要な場所のことです。
2023年夏、国立科学博物館(科博)が、収集・保存してきた膨大なコレクションの維持と活動継続の支援を募るため、クラウドファンディングを実施したことが大きな話題になりました。このとき初めて、収蔵庫という存在を知った、それを維持していく困難さに関心を持った、という方も多かったことでしょう。
収蔵庫は、ミュージアムにとって保存すべきと判断した貴重な品々を、大切に守りながら後世に伝える大きな役割を担っています。そのため、必要十分な広さや万全のセキュリティ対策はもちろん、できるだけ一定の温度と湿度を保つための空調を稼働させています。また、害虫の侵入を防いだり、地震や火事、台風や洪水などの災害にも耐えられる堅牢な設備であることも重要です。
しかし、現在、全国各地のミュージアムで、収集してきた貴重なコレクションや資料群が、収蔵庫に納まりきらない、という「収蔵庫不足」が深刻化しています。
加えて、昨今の燃料費高騰などの影響で、施設の維持にかかるコストが増加。ミュージアムの運営にも大きな負担を強いられ、全国各地のミュージアムと収蔵庫が、存続の危機に直面している、と言っても過言ではありません。
そこで今回、学芸員として複数のミュージアムに勤務された経験を活かしながら、収蔵庫と「収蔵展示」の研究に取り組んでいる、金沢学院大学 准教授の加藤謙一さんをお招きし、収蔵庫やコレクションを巡る様々な課題、これからのミュージアムと収蔵庫の在り方などについて、お話しを伺いました。

プロフィール
加藤謙一さん (写真中央)
金沢学院大学 芸術学部 芸術学科 准教授
関西大学大学院 文学研究科 史学専攻を修了後、国立民族学博物館 文化資源研究センター機関研究員、長崎歴史文化博物館 教育グループ研究員、金沢美術工芸大学 美術工芸研究所 学芸員を経て、2019年より現職。専門は「博物館学」と「収蔵展示」。
<対談者>
森 誠一朗 (写真左)
クリエイティブ本部 プランニングプロデュースセンター 企画2部 第7ルームチーフ
大学卒業後、5年半の博物館勤務を経て乃村工藝社に中途入社。
入社以来、国や市町村、企業が設置するさまざまなミュージアムの展示づくりの仕事に携わり、老若男女すべての人に、いかに展示対象の魅力を伝え、楽しんでもらえるかを追求している。
井戸 幸一 (写真右)
クリエイティブ本部 プランニングプロデュースセンターセンター 企画2部 第7ルーム
博物館学芸員という前職の経験を活かしながら、現場を見て考え、お客さまとともに悩み、ゴールを目指す空間づくりを追求し、人文系を中心とした行政や企業のミュージアムに関わっている。
コレクションを死蔵させず、活用するための「収蔵展示」
ミュージアムで展示される資料は、収蔵庫にあるコレクションのほんの一部です。この課題に早くから着目してきた欧米で生まれたのが「Visible storage(ヴィジブル・ストレージ)」、つまり「収蔵展示」や「見せる収蔵庫」という仕組みです。
森
まずは、加藤さんが「収蔵展示」に着目されたきっかけをお聞かせください。
加藤さん
私が学芸員として在籍していた金沢美術工芸大学(金沢美大)で、金沢市と共に「平成の百工比照(ひゃっこうひしょう)」という事業に取り組んだことがきっかけです。これは現代の工芸に関する材料や道具、技法や製作工程、実際に流通している製品など、工芸に関する標本資料を収集するものでした。
のちに収集した約5,600点に及ぶ資料を紹介する展覧会を開催することになり、収集した資料を展示も保管もできる保存箱に収納するシステムをつくりました。大学美術館として、学生や教員らが研究の際、これらの保存箱を手に取れるような仕組みを、と考えた結果が「収蔵展示」だったのです。

平成の百工比照 展示・閲覧コーナー
これは図書館の開架書庫から本を取り出し、閲覧テーブルで確認できるような仕組みと似たもので、金沢美大の旧キャンパス内にあった「美術工芸研究所ギャラリー」に、保存箱の収納棚と、閲覧用のテーブルなどを設置しました。
この空間をつくるにあたり、「収蔵展示」に関する事例をインターネットなどで調べたものの、数える程度しかなく、体系的な調査や効果測定、課題の検証といった情報はほとんど見当たりませんでした。それなら自分で研究しよう、と取り組む過程で、収蔵庫が抱える問題にも関心が向いていきました。
森
そうでしたか。つまり、収蔵したコレクションや資料を単に保存するだけではなく、どうやって活用するか、がもともとの起点だったんですね。
加藤さん
はい。ご存知の通り、資料の保存のためには、展示しないで大切に保管しておいた方が良いのですが、それではせっかくの資料が後世に活かされません。「保存」と「活用」は相反するものですが、いかに両立させるか、が大切です。
私の"活用から保存を考える"というスタンスは、おそらく大阪の国立民族学博物館(みんぱく)での勤務経験で培われたもので、金沢美大へ移って、改めて考えるようになりました。
森
そもそも、欧米や日本における「収蔵展示」や「見える収蔵庫」は、いつ頃から始まったのでしょうか。
加藤さん
海外における「収蔵展示」の先駆けと言われているのは、カナダのブリティッシュコロンビア大学(UBC)人類学博物館です。私もまだ調査中ですが、1976年に、学生や研究者らが使いやすいように、と、なるべくたくさんのコレクションが見えるような収蔵庫が生まれました。
一方、日本では、1971年に開館した北海道開拓記念館の収蔵陳列室が最初とされています。北海道博物館の前身の施設ですね。収蔵陳列室がいつ頃設置されたのか、また、当時、欧米の影響を受けていたのか、はわかりかねるのですが、『博物館学事典』によると、日本の理科教育を開拓し、博物館の基礎を築いたと言われる博物館学者、棚橋源太郎が提唱した「二元展示論」を具体化したものだったそうです。一般の鑑賞者がわかりやすい内容を意識して構成される常設展示室とは異なり、地学や生物学、民族学など、研究者や専門家の学問領域に即した分類展示が行われていた、と記録に残っています。
そして特筆すべきは、2005年に開館した九州国立博物館でしょう。収蔵庫にガラス窓が設置されたことは画期的でした。バックヤードですので、いつでも誰でも見学できる環境ではありませんが、国立の施設で"収蔵庫を見せる"という取り組みが実現したことは、他館へ「見せる収蔵庫」が知られる大きなきっかけになりました。
「バックヤードこそ、面白い」ミュージアムの"裏側"を伝える重要性
ミュージアムの心臓部とも言えるほど大切な場所である収蔵庫。しかし、大切にするあまり、その存在や重要性を市民に知ってもらうきっかけがなく、収蔵庫が抱える課題や窮状が伝わりにくい、ひいてはミュージアムの社会的な価値すらも伝わっていかないのでは。加藤さんはそんな問題意識と危機感を抱いています。
加藤さん
ミュージアムの「展示」の裏側には、資料を収集し、長期的に保存し、研究する、という営みがあり、保存や修復などのメンテナンスに日々携わっている方々がいます。これらの仕事がなければ、展示はできません。結局、収蔵庫のことだけを伝えるのではなく、ミュージアムを支える様々な裏側の仕事も含め、全体を繋げて伝えることが大切なのです。
例えば「バックヤードツアー」などを通して、裏側の仕事を知ってもらい、多くの市民に、ミュージアムが持つ価値や役割に対する関心や理解を得られるような取り組みが欠かせません。
また、私のそもそもの問題意識の前提に、裏側をきちんと伝えないと、ミュージアムの社会的な価値が市民や地域の方々に伝わらないのではないか、という考えがあります。現在、私は大学で、学芸員を目指す学生が履修する、博物館学の授業も担当していますが、これからの学芸員は単に研究成果を展示で見せるだけではなく、その裏側にある価値や自分たちの活動を伝え、理解を得るという意識が必要なのでは、と。特にミュージアムの核である収蔵庫とその営みをどう伝えていくのか、はとても重要だと考えています。
井戸
普段はなかなか見えてこない「裏側」が面白い、というのはミュージアムに限らず言えることかもしれませんし、伝える必要性を感じます。
加藤さん
一方、収蔵庫のことを全く知らない人にも伝えていかなければならない中で、どうしたらいいのか。そのヒントになったのが、秋田県の横手市増田まんが美術館に設置された「マンガの蔵展示室」でした。
ここは「原画収蔵庫」と、原画のデジタルアーカイブ作業などを行う「アーカイブルーム」で構成され、まさにバックヤードと展示室をつなぐ機能を果たしていると言えます。
加えてここには、原画をじっくり見られる引き出し付きのキャビネット「ヒキダシステム」があり、上から順に原画の入った引き出しを開けると、1話分の漫画を読むことができます。

横手市増田まんが美術館「マンガの蔵展示室」
また、群馬県渋川市にある、現代アートのミュージアム、原美術館ARCでは、通常非公開の「開架式収蔵庫」を案内してくれる事前予約制のツアーが不定期で開催されています。しかも、一般的な収蔵庫は作品の配架位置が決まっているものですが、ここでは定期的に配置換えを行い、収蔵庫という空間や文脈の中で作品をどう見せるか、というキュレーションのような取り組みまで収蔵庫の中で行われているのです。

原美術館ARCの開架式収蔵庫(撮影:齋藤さだむ)
井戸
それはとても興味深いです。もちろん、コレクション群を大切に扱わなければなりませんし、一般の方々が分かりやすい文脈でどう伝えるか、も重要ですが、館の裏側を見せる、つまり、館の活動をもっと知ってもらうためには、展示だけではなく、収蔵庫や運営などもセットで考える視点が、本当に必要ですね。
加藤さん
20年、30年先の ミュージアムが、市民にとって本当に意味のあるものとして認知されている、今まで以上に社会の中に存在し続けていられるためにも、収蔵庫や調査研究といったミュージアムの裏側に価値を見出し、その営みをお見せするような姿勢や取り組みが大切ですね。
「ミュージアムのこれから」のために、それぞれができることを考える
加藤さん
新潟県立歴史博物館で長年にわたり学芸員として勤めた山本哲也さん(現在、國學院大學)が取り組まれ、また調査も進めている「博物館学展示」にも注目しています。これは、保存修復の営みを見せる展示や、展覧会ができるまでプロセスを見せる展示、学芸員の調査研究について紹介する展示など、展覧会の形式で様々な裏側を見せる取り組みです。
ここ数年で「博物館学展示」が増えた背景には、コロナ禍によってミュージアムが臨時休館になったり、他館と作品や資料を貸し借りできなくなったことが一因であると考えます。それによって、自館のコレクションに改めて目を向けたり、社会におけるミュージアムの意味を考えたりしたことがあったのではないでしょうか。
井戸
そうですね。ミュージアムの中の人間が改めて、プロセスを見せる面白さや、見えないものを見えるようにする意味・意義を再認識した機会だったのかもしれません。
森
ここまで「見える収蔵庫」をはじめとする様々な取り組みについて話してきましたが、最後に、加藤さんは、これからのミュージアムにどんなことが大切だとお考えでしょうか。そして、我々のようなミュージアムプランナーは、どんな役割を担うべきでしょうか。
加藤さん
乃村工藝社の皆さんは、すでに多くのノウハウをお持ちの専門家であり、改修や増築、新築など、ミュージアムが何か新しいことをするタイミングに関わることが多いですよね。なので、ぜひ積極的にミュージアムの価値を見出して面白がってもらい、見せ方や伝え方について様々な提案をしてもらいたいです。
先ほど「バックヤードツアー」の話が出てきましたが、ミュージアムの中で働いていると、バックヤードは単なる執務エリアで、展示室のような華やかさも見るべきものもない、と考えがちですし、変わりたくても変われない、どうしても保守的になりがちな現場も多いだろうと想像します。
しかし外部の皆さんは、とても面白くて価値あるものや場所だ、ととらえてくれていますよね。その視点や考え方を、ミュージアムの側が大切にできるかどうか。「市民の方々はこういうところを面白いと思ってくれるのか!」という新たな気づきや、変化のきっかけにできるかどうか、それこそがミュージアムが生き残っていく上で大事なポイントになるのでは、と考えています。
合わせて、私が最近読んだ文献の中で、収蔵庫の内部に鑑賞者が立ち入ることの"3つの価値"が挙げられていたので、紹介させてください(注1)。
まずは「偶然性」。コレクション群の中からその人が興味関心を持つものと出会う、偶然性の価値です。
次に「透明性」。これまで秘匿されていた空間に入ることで、新たに確保される価値ですね。
最後が「驚き」です。収蔵庫にはこれだけの物量があるのか、こんなに価値のあるものがコレクションされているのか、これだけのコストや技術、ノウハウでコレクションを未来に残そうとしてるのか、といった「驚き」が価値になる、と述べられていました。
これら3つの価値を得た鑑賞者に、ミュージアムのスタッフがどのように関わるのか、というバランスも大切です。鑑賞者が偶然見つけて面白いと思っているときに、どんなタイミングで、どのように声をかけるのか。ボランティアの方でも学芸員でも、誰が担っても良いのですが、重要なことだと思います。
森
なるほど。
加藤さん
また、ここまで述べてきた取り組みを、ミュージアムの側だけが対応しなければならない、という訳ではないと考えます。ミュージアムは市民のための開かれた場であり、市民はミュージアムのコレクションへの「アクセス権」を持っているはずです。"権利"があるなら、市民の側からもっとコレクションの保存と活用に積極的に関与する"義務"も生じる、とは考えられないでしょうか。この”義務”の側面はこれまであまり注目されてこなかった視点だと感じています。
私たちの"宝"であるミュージアムのコレクションや資料群を、市民である私たちがどのように守り伝えていくのか、を共に考えて行動する"義務"がある。
その意味で、現在直面する「収蔵庫」の危機は、皆で改めて「収蔵庫」を考える良いタイミング、なのかもしれません。
森
「収蔵展示」や「見せる収蔵庫」には、より多くのコレクションを活用するといった側面に加えて、さまざまな困難に直面する収蔵庫やコレクションについて、市民とともに考える場としての役割も期待されますね。
本日は、非常に示唆に富むお話をありがとうございました。
注1
Sarah,Bond(2018)”Serendipity,Transparency, and Wonder: The Value of Visitable Storage,” in Mirjam Brusius and kavita Singh(eds.), Museum Storage and Meaning: Tales from the Crypt, pp.64-82.
【収蔵展示の導入事例】
〇長崎歴史文化博物館:「長崎の美術・工芸」展示室(2005年)
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/nagasaki-museum-of-history-and-culture/
〇能美ふるさとミュージアム(2020年)
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/nomi-furusato-museum/
〇設楽町奥三河郷土館(2021年)
https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/shitara-town-oku-mikawa-folk-museum/
文:naomi
この記事は気に入りましたか?