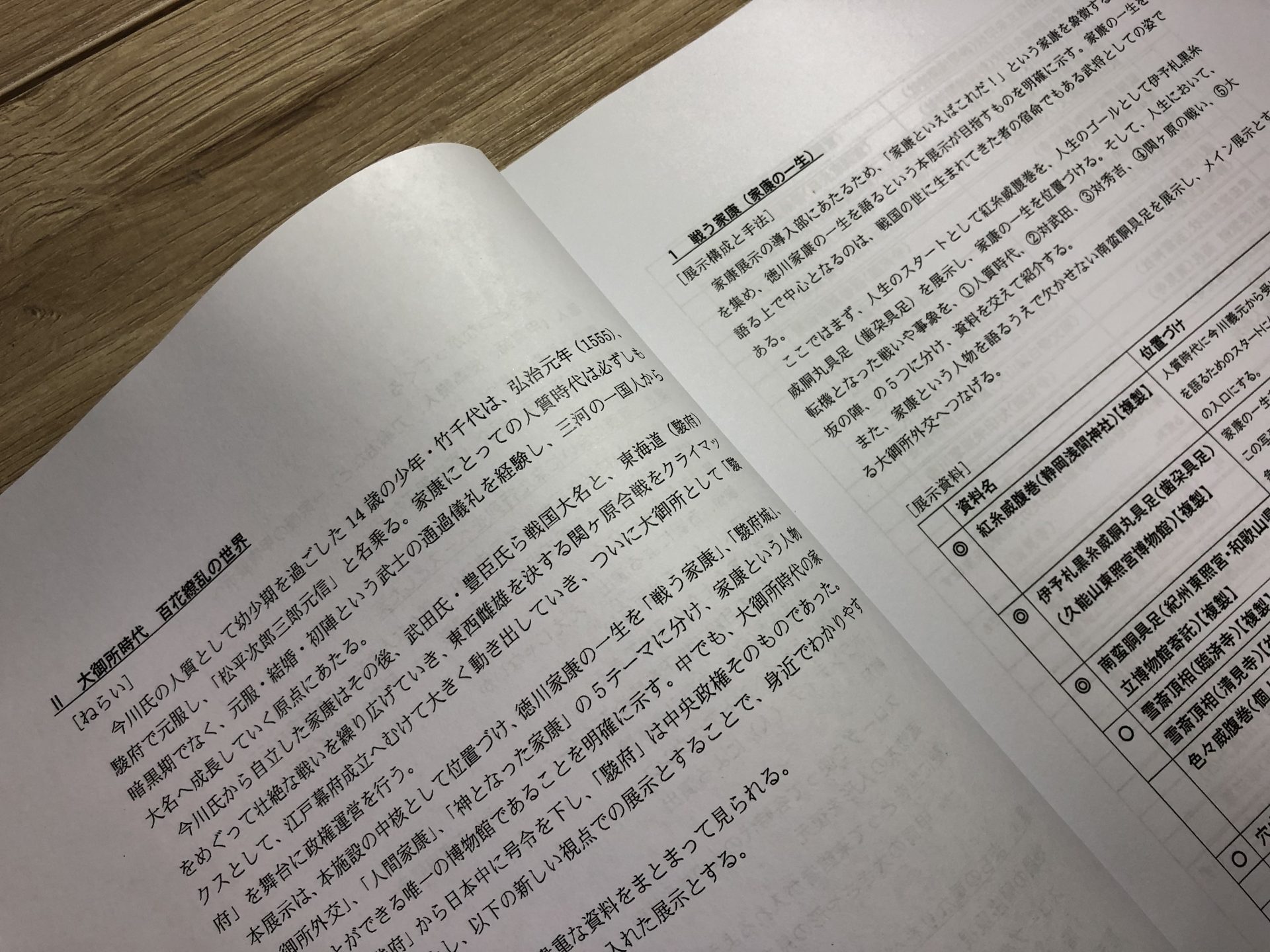- text and edit by
- 嵩 恵奈
静岡市歴史博物館のグランドオープンより約2年。
静岡市に歴史博物館ができる意味を深堀りするシリーズとして、第三弾となる今回は、近世の展示を担当した学芸員の増田亜矢乃さん、近代の展示を担当した太田那優さん(2022年当時)、そしてジオラマや模型などの実際の展示制作を担当した乃村工藝社テクニカルディレクター遠藤信之の3名にお話を伺います。インタビュアーは、乃村工藝社プランニングディレクター森誠一朗が担当しています。
*インタビューはグランドオープン前の2022年7月に行いました。
近世・近代の展示では、”江戸時代の静岡浅間神社の廿日会祭(はつかえさい)の行列風景”と”昭和30年代の静岡市街地”の2つの模型が制作されました。歴史博物館にふさわしい展示物とするため、それぞれの模型は歴史的検証を含めて、どのような手順で制作されたのか、企画意図から資料の収集、検証などを経て展示が完成するまでを、それぞれの立場から、苦労した点、来館者へのメッセージなどを交えて語っていただきます。
徳川家康をはじめ、歴史上の人物も見物した廿日会祭
森
まず、増田さんがこのプロジェクトに関わることになった経緯を教えていただけますか。
増田さん
2011年、静岡市歴史博物館の基本構想が策定され、学芸業務ができる人の募集がかかりました。当時私は大学院に在学中だったのですが応募して非常勤として採用になり、歴史資料の調査を5年間務めました。必要な資料の調査はもちろん、最終的には調査成果を展示する「さきがけ企画展」の企画・運営にも従事しました。
その後、他の博物館の学芸員として働いていたのですが、静岡市歴史博物館の開館前に学芸員の募集があることを知り応募し、採用していただきました。私が入ったのは2021年、展示をつくっている真最中でした。
 近世の展示を担当した増田亜矢乃さん。博物館設立の初期段階にも資料調査などに携わってきた
近世の展示を担当した増田亜矢乃さん。博物館設立の初期段階にも資料調査などに携わってきた
森
ご担当の近世展示についてお伺いします。近世の展示で紹介される「廿日会祭(はつかえさい)」というのはどんなお祭りなのか教えてください。
増田さん
実は「廿日会祭」の起源ははっきり分かっていませんが、もともとは市内にある建穂寺(たきょうじ)で行われていた廿日会という仏教行事であったようです。この行事で舞われていた「稚児舞楽」がいつからか静岡浅間神社でも奉納されるようになったようです。戦国時代末期には、公家の山科言継が静岡浅間神社で「稚児舞楽」を観たという記録が残っていて、江戸時代には徳川家康の息子の義直や頼宣も見ているなど、古くから静岡市で親しまれてきたお祭りです。
江戸時代には城下町の町人たちが「お踟(ねり)」とよばれる行列を出して、建穂寺から来る稚児を迎え、静岡浅間神社まで練り歩きました。当時の「お踟」は趣向をこらした仮装や豪華な屋台からなる行列でした。江戸時代の中頃には行われていたことが資料からわかっています。旧暦2月20日前後に行われていたこのお祭りは、現在では4月1日~6日にかけて行われています。
森
「廿日会祭」は、静岡の市民にとってどんなお祭りなのでしょうか。
増田さん
近世では、駿府の人たちに経済的利益をもたらし、自分たちの誇りになる行事だったと思います。江戸時代には、駿府だけでなく近隣の地域からも大勢の人たちが見物に来ていたという資料も残っています。
静岡浅間神社は静岡市民のよりどころでもあり、「廿日会祭」は静岡市の歴史文化を継承・体現してくれているお祭りといえます。
江戸時代に書かれた記録を参考に「お踟(ねり)」を立体化
森
この「廿日会祭」の「お踟」の様子を、模型にして再現したわけですが、模型を制作する上で参考にした資料はありますか。
増田さん
模型をつくる動機になった古い絵画資料が3冊あり、これをもとに模型をつくることになりました。人宿町三丁目で左官の棟梁をしていた人が絵師につくらせた貴重な古文書です。
絵が描かれた冊子には、「お踟」の要素がひとつひとつ細かく描いてあり、文字の冊子は、何月何日にこういう準備をしたとか、こういう生地の着物を使ったという記録が詳細に記されています。弘化五(1848)年のことなのですが、当時の「お踟」の様子が非常によくわかります。
江戸時代の資料を集め、描かれていない部分も再現
森
平面的な絵図資料を立体的な模型にする上で苦労された点、工夫された点があれば教えてください。
遠藤
彩色されている絵図があったのは、立体化するにあたりとても助かりました。絵図自体、非常によく描けていて味がある。ただ完全にデッサンされているわけではないので、それを破綻させないようにどう立体化するか、絵のイメージをどこまで再現できるか、それを念頭に作業しました。
また、絵の見えない部分はどうなっているか、増田さんにいろいろ資料を集めていただき、それをもとにつくっていきました。
 造形責任者を務めた遠藤信之。長年、歴史系を中心としたジオラマや模型など数々の造形制作に携わってきた
造形責任者を務めた遠藤信之。長年、歴史系を中心としたジオラマや模型など数々の造形制作に携わってきた
増田さん
絵図の人物が正面を向いていると当然背面の部分は見えませんが、後帯の結び方はどうなっているのか、紐は後ろまで回っているのかなど、それがわからないと立体化できません。江戸時代の帯の結び方を調べようと、論文を引き出したりしました。着物の柄も、東海道の名所図会などの資料を参考に、遠藤さんと相談しながらつくっていきました。
 CGと絵図とを比較し、議論を重ねながら、造形の表現を検討していく
CGと絵図とを比較し、議論を重ねながら、造形の表現を検討していく
森
絵の持つイメージをどう再現するかというお話ですが、他にも工夫した点はありますか。
遠藤
たとえばフィギュアで顔をつくるときには、肌を肌色に塗るだけじゃなく、そこに影を入れて実在感を出していきます。でも絵図の絵はそういう描き方をしていない。影を入れれば立体的になるのですが、そうすると元絵本来の味わいからどんどん離れていってしまう。その匙加減が大変でした。
増田さん
元の絵図は、駿府の高名な絵師が描いているのですが、遠藤さんに「しっかり色付けすると風合いが出ないよ」と言われて。
遠藤
油絵のように何度も色を載せてカタチをつくっているわけではなく、着物の柄も人物も筆で、一発で描いている淡彩みたいにふわっとしていて味があるのが特徴です。
 着彩前の人物造形|服のしわや、髷、指の先も丁寧に掘り出していく
着彩前の人物造形|服のしわや、髷、指の先も丁寧に掘り出していく
 完成後の人物造形|絵図の世界観を大切にしながら、廿日会祭の臨場感も表現した
完成後の人物造形|絵図の世界観を大切にしながら、廿日会祭の臨場感も表現した
交流を通して、一緒に成長していける歴史博物館に
森
この模型を通して、来館者に伝えたいメッセージがあればお聞かせください。
増田さん
美術系の展示であれば、見てキレイだなとか、心に訴えかけるものがあると思うのですが、歴史系の展示は文章が多くなり、ストレートに伝わらないことがあります。そういう中で模型ならば、静岡の江戸時代にこんなにぎやかなお祭りがあったことを視覚的に感じてもらえるのかな、と。
静岡は戦災や大火にみまわれて、昔を伝える資料がなにもない、とよく言われるのですが、こうやって江戸時代の駿府の人たちに息づいていたお祭りがある。来館される方には、当時の駿府の人たちが生き生きと祭りを楽しむ姿を、ぜひ見ていただきたいなと思います。
森
「廿日会祭」は駿府だけでなく、近隣地域からも見物にくるお祭りだったことを、私自身も初めて知りました。あらためて、もっと「廿日会祭」や「稚児舞楽」、「お踟」に光が当たるといいなと思いました。
最後の質問になりますが、静岡市、あるいは市民の方々にとって、博物館がどんな施設になってほしいか、お聞かせください。
増田さん
歴史博物館の1階は、無料でどなたでも入れるスペースになっています。歴史に興味がある方はもちろん、そうじゃない方もふらっと立ち寄って、いろんな方が気軽に歴史に触れられる。そういう中でいろんな交流が生まれてくるのではないかなと思います。
来館者、学芸員、ボランティアなど、博物館に集う人々が交流を通して一緒に成長していける。そんな博物館になって10年後を迎えられるといいなと思っています。
高度成長期直前の静岡市街地を精密な模型で再現
森
ありがとうございました。続いて、近代を担当した太田さんにお話を伺いたいと思います。太田さんが本プロジェクトに関わることになった経緯をお聞かせください。
太田さん
私は出身が浜松で、大学は京都だったのですが、静岡で就職したいと思い、こちらの募集を見て応募しました。
森
太田さんが歴史に興味を持ったきっかけはなんだったのでしょうか。博物館の原体験のようなものはあったのでしょうか。
太田さん
子供の頃、奈良に連れて行ってもらい法隆寺を見たのが歴史の原体験になっています。
歴史の教科書に出てくるものを、目の前で見るインパクトはすごく大きなものでした。実物に触れたという体験が、私が歴史を仕事にするきっかけになったと思います。
また大学在学中、大学博物館の「子ども博物館」というイベントのスタッフをして、自分たちが考えたワークショップに、毎週参加する常連の子どもたちがいました。その子どもたちがワークショップをしている間、親御さんはブースの大学生と話をしたり、展示を見たりしている。
まさに博物館が交流や学びの場になることを体感し、一度来て終わりの施設ではなく、何度も足を運んでもらえる博物館っていいなと、実感しました。
 近代の展示を担当した太田 那優さん。膨大な写真資料と向き合い、昭和30年代の静岡市街の再現に取り組んだ
近代の展示を担当した太田 那優さん。膨大な写真資料と向き合い、昭和30年代の静岡市街の再現に取り組んだ
森
太田さんご担当の近代の展示で、昭和30年代の静岡市の市街地を模型にすることになった経緯を教えてください。
(注) 3階の展示室では、まちと人にスポットを当て、昭和戦後の静岡の市街地を巨大なジオラマにして展示。路面電車や道路、公園をはじめ、様々なランドマーク、建物の一軒一軒まで、リアルな立体模型として再現されている。ここでは、ひと目でわかる都市模型で、わかりやすく静岡市の時代の変遷を伝えている。
太田さん
静岡市が昭和36(1961)年の市街地の高精細な航空写真を持っていたことが模型をつくる契機になりました。航空写真からは高度成長期で姿が大きく変わる前のまちの様子がわかります。昭和37(1962)年に市内の路面電車が廃止になるのですが、路面電車が走っていた頃の静岡市の姿を見せていきたいね、ということで、模型を制作することになりました。
模型制作のため、1,000点以上の写真が集まる
森
実際に都市模型を制作するにあたり、市民から当時の写真を集めたと伺っています。どのような方法で集めたのでしょうか。また、何点ほどの写真が集まったのかを教えてください。
太田さん
静岡市の「さきがけミュージアム」というサイト内のブログでの告知やチラシを配って、市民から昭和30年代の写真を募集し、最終的には1,000点以上の写真が集まりました。そのうち建物が写っていて、場所を特定できる写真にはナンバリングをしました。ナンバリングされた写真は700点以上になります。ほかにも提供者が市役所の窓口に持ってきてくれたり、提供者のご自宅に伺って写真を見せてもらうこともありました。
ただ、当時の写真が手に入っても、最初はどうすればいいかわからない状態で、整理する方法すら決まっていませんでした。ひとりで見ていると着眼点もわからないので、もうひとりの担当者と一緒に写真を囲み、「ああじゃないか、こうじゃないか」と悩み、相談しながらのスタートでした。
 昭和30年代の市街地模型を製作するきっかけとなった昭和36(1961)年の航空写真と同時代の住宅地図
昭和30年代の市街地模型を製作するきっかけとなった昭和36(1961)年の航空写真と同時代の住宅地図
森
写真以外で参考にした資料はあるのでしょうか。
太田さん
昭和35(1960)年の住宅地図も参考にしました。手書きで名前が書き込んである地図だったので、写真に映る建物や道路を地図と見比べていくと、「これって、この建物だよね」と、だんだんわかるようになってきました。
ただ、この時代は想像以上にカラー写真が少なく、色がわからないという問題があり、建物の色がわかる資料を探すなかで「静岡映画館物語」編集委員会『映画館 わが青春のスクリーン 静岡映画館物語』[平成21(2009)年発行]という本に出合いました。当時、七間町にあった映画館街についてまとめた本ですが、絵や写真がたくさん載っていたので、とても参考になりました。
ネオンサインの正確な色を、誰も覚えていなかった
森
航空写真や地図をもとに写真をピックアップし、書籍も参考にしながら立体にしていったということですね、膨大な資料を読み取っていく苦労とか、工夫した点があれば教えてください。
遠藤
ナンバリングした写真のなかで、使えるものを選別してプリントし、地図上でここだなと思うところに貼っていきました。写真があるものは建物のカタチが明確で、それをベースに再現しました。また、1961年の航空写真はすごく精細なものだったので、航空写真を使って立体化しました。上から見て建物の横の部分が写っているものはそれを持ち上げて立体化する。写真が一切ないところは、昭和42(1967)年のカラー写真を航空写真と照らし合わせながら立体化しました。
 製作途中の市街地模型
製作途中の市街地模型
太田さん
模型のモデルとなった1961年はちょうどまちの開発が始まる頃で、道路が工事中のところもありました。遠藤さんから「道路ができた状態にしましょうか」と言われたのですが、工事が終わった状態だと大きく道が変わってしまうので、工事中の場所は工事中のまま立体化してもらいました。
昭和30年代当時は、今より写真が貴重な時代だったので、すごく大きな建物でも写真がないものもありました。どうしてもわからないところは、他の写真から類推して再現していきました。
 道路上に取り残された家から、道路整備の最中であることが読み取れる
道路上に取り残された家から、道路整備の最中であることが読み取れる
増田さん
私は、駅前にあったネオン看板の色がわからないことがすごく衝撃でした。あんなにイメージが強いものなのに、誰もわからなかったのです。
太田さん
複数の人に聞くと「黄色だよ」という人や、「青だった」と言い張る人がいたり。結局、ネオンのカタチから私たちで色合いを決めました。そういう意味では、この模型はこれで完成、というよりも、開館後いろいろな人が見て、意見をもらい、資料がさらに集まり、この模型の間違いを修正していければいいと考えています。そうやって、この模型をもっと成長させていきたいと思っています。
静岡市民の人生の瞬間を紡ぎ、形になった都市模型
森
模型が出発点になって、みんなの静岡の記憶がどんどん反映されていくということですね。
遠藤
そうですね。これは模型だけを見れば1961年のまちの模型ですが、つくられた過程や、表現した中身を考えると、すごく新しい模型だと思います。たとえば江戸時代の城下町を再現するとなると、研究家に話を聞いたり、専門家が図面を引いたり、発掘状況からつくることになるのですが、今回の場合は市民から集めたリアルな情報を基にしている点が全然違います。情報をこういうカタチで残していくこと、蓄積していくことは、これまでの歴史模型とは一線を画していると思います。
太田さん
歴史って、名前もわからない一人ひとりの人生が積み重なって紡がれていくものだと思います。この模型は、”建て替えのタイミングで家の写真を撮った”とか、”お祭りのときに記念写真を撮った”とか、一人ひとりの人生の瞬間を切り取った写真を集めて生まれました。その意味で、この模型は昭和30年代の静岡市民の人生を紡いだ模型だと言えるのではないでしょうか。
森
模型が一つの核となって、いろんな人の記憶が積み上がり、集約されていくような展示になれば本当に素敵ですね。
今のお話にも重なりますが、この模型を通して来館者に伝えたいメッセージがあれば教えてください。
太田さん
実は静岡の市街地は、江戸時代からまちのカタチが大きく変わっていません。子どもたちがおじいちゃんやおばあちゃんと一緒に模型を見ても「この場所は、今はこんなふうになったんだね」というのがわかるんですよ。だから都市模型を通して、世代を超えたコミュニケーションが発生しうると思います。歴史は遠い場所ではなく、地続きで、身近にあるもの、つながって今ここにあるものだということを感じてもらえれば、と思います。
 昭和30年代の模型の静岡駅前周辺。左に富士山をかたどったネオンサインが見える
昭和30年代の模型の静岡駅前周辺。左に富士山をかたどったネオンサインが見える
森
最後に、歴史博物館が静岡市にとってどんな施設になって欲しいかお聞かせください。
太田さん
博物館は難しい、敷居が高いと思われがちですが、それをどうにかできないかなと。博物館が一方的に発信するのではなく、市民から教えてもらったことを展示にしたり、子どもたちの素朴な疑問や意見をもらって、それを一緒に解決していったり。研究者と市民の皆さまをつなぐ施設、市民と一緒に歩いていける博物館になればいいのかなと思います。
森
開館前に完成させるのではなく、開館後に答え合わせしながら修正されていく展示、という発想は、私たちのような展示づくりを担当する人間にとってはとても新鮮でした。本日はありがとうございました。
 昭和30年代の静岡市街地の模型を囲む学芸員の増田さん、太田さんと乃村工藝社のプロジェクトメンバー
昭和30年代の静岡市街地の模型を囲む学芸員の増田さん、太田さんと乃村工藝社のプロジェクトメンバー
この記事は気に入りましたか?